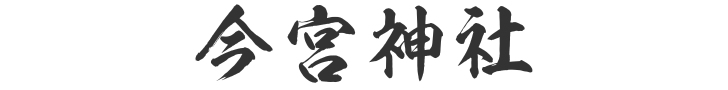今からおよそ1000年前の平安時代。京の都では、たび重なる疫病の流行により、多くの人々が苦しんでいました。人々の不安と混乱が続く中、長和4年(1015年)、時の天皇・三条天皇の勅命により、一つの神社が建立されました。それが、ここ花園の地に鎮座する「今宮神社」です。
当時、疫病は神仏の怒りによるものと信じられており、その災いを鎮めるために「御霊会(ごりょうえ)」という神事が行われていました。今宮神社もまた、疫神を鎮め、地域の安寧と人々の健康を願って創建された、いわば「疫病退散の神社」だったのです。
その後も、1052年には再び疫病が流行し、後冷泉天皇の命によって社殿が整備され、御霊会が盛大に営まれました。このことからも、今宮神社がいかに人々の命と暮らしに深く関わってきたかがうかがえます。
そして時は流れ、江戸時代。1644年には仁和寺門跡・覚深法親王の発願により、徳川家光の助力のもと、本殿や拝殿、末社が再建されました。これらの建築は現在も大切に守られ、京都市の有形文化財として登録されています。
現代の私たちにとって「疫病」という言葉は、決して過去のものではありません。近年の感染症の流行を経験した私たちにとって、疫病退散を願って創建された今宮神社の存在は、どこか心強く感じられるのではないでしょうか。
花園の地で静かに時を刻み続ける今宮神社。境内に足を踏み入れると、どこか厳かな空気とともに、1000年の時を超えて受け継がれてきた「祈りの力」を感じることができます。
地域の皆さまの健康と安全を願い、今も変わらず、この地を見守り続けている今宮神社。どうぞ季節の折々に、静かに手を合わせにいらしてください。