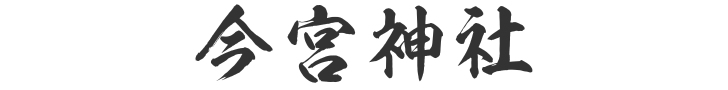花園の町に、静かに息づく今宮神社。その小ぢんまりとした境内には、実は京都市の有形文化財にも指定された、貴重な歴史的建築が残されています。
中でも注目すべきは、本殿。江戸時代の寛永21年(1644年)、仁和寺門跡・覚深法親王の願いにより、徳川家光の支援を受けて再建されたものです。建築様式は「一間社流造(いっけんしゃながれづくり)」と呼ばれ、流れるように美しい屋根の曲線が特徴です。屋根は檜皮葺(ひわだぶき)。木の皮を何層にも重ねて葺く、昔ながらの技法で、風格と落ち着きを感じさせてくれます。
本殿のすぐ前にある拝殿は、参拝者が祈りを捧げるための場所。手を合わせて見上げれば、歴史を経た木の色合いに、時の重みと荘厳さがにじみ出ています。
さらに境内の奥には、松尾神社という末社も鎮座しています。こちらには、大山咋命(おおやまくいのみこと)と倉稲魂大神(うかのみたまのおおかみ)が祀られており、五穀豊穣や商売繁盛のご利益があるとされています。今宮神社が疫病退散だけでなく、暮らしの様々な願いに応えてくれる神社であることを、こうした末社の存在が物語ってくれます。
これらの社殿群は、1984年に京都市の文化財に指定されました。ただ古いだけではありません。幾度の災害や社会の変化を乗り越えながら、今に受け継がれているという“歴史の重み”が、そこにはあります。
近代的な建物が並ぶまちの中で、今宮神社の社殿は、まるで時が止まっているかのように感じられるかもしれません。しかし、それは決して過去の遺物ではなく、花園の人々の暮らしや祈りとともに、静かに生き続けている「文化そのもの」なのです。
日々の忙しさの中で、ふと立ち止まって眺めてみてください。千年を超えて守られてきた美しさが、そこには息づいています。